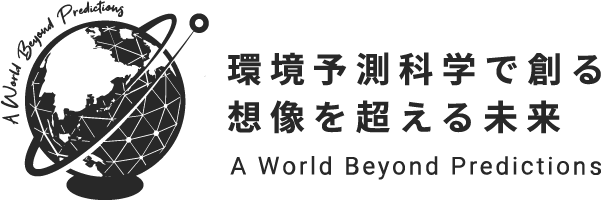海上豪雨を起こし、陸域豪雨を緩和するために有効な介入操作を発見する
最近の地球温暖化の進行に伴って、世界の様々な場所で豪雨がより頻繁に発生するようになっています。日本も例外ではなく、「線状降水帯」とよばれる特定の地域に数時間にわたって停滞する細長い形状をもった降水システムによる豪雨が増えているとの指摘があります。
こうした背景において、本プロジェクト「海上豪雨生成で実現する集中豪雨被害から解放される未来」では、海上豪雨を人為的に強化することで、下流の陸上の豪雨を減少させることを狙っています。具体的には、「人が住む陸上ではなく、上流にあたる海上で“何らかの刺激”によって降水を生じさせて雨の種となる水蒸気を減らしてしまおう」というものです。
梅雨の時期に関して、上流に位置する東シナ海では暖かい海面からの蒸発や南西側からの大量の水蒸気の輸送によって積乱雲が容易に発達できるような環境が整っています。実際にこの時期の降水を注意深く眺めると、九州の西側の小さな島をきっかけにして、その下流で降水が連なって発達する様子が確認できます。
こうした気象学的な知見から、項目5「海上豪雨生成に有効な介入操作の検討」では、(人間による)“少し”の刺激であっても海上での人為的な降水の生成・強化が可能ではないかと考えて、梅雨期の豪雨事例を対象に、陸上の降水の抑制につながるような介入操作について調べています。具体的には、「どのような場合に、どのような手法であれば有効な介入が可能か?」を明らかにすることを目標にして、過去に生じた豪雨事例を様々な物理量を用いて整理すると共に、数値気象モデルを使って再現して、そこに“現実的”と考えられる気象介入の手段を試して有効性を確認するという作業を進めています。
研究開発課題5-1気象モデルを用いた介入操作の有効性評価
研究開発課題推進者: 安永 数明(項目長)
研究概要
数値気象予測モデル(SCALE)を用いて、気象介入手段(洋上ドーム形成、冷気塊形成、海面水温冷却、マイクロ波加熱、シーディングなど)の有効性を明らかにします。特に気象学的見地から、海上豪雨を起こすために有効な介入操作を発見します。
また研究後期においては、航空機・船舶・気象レーダーを伴う屋外実験を計画(手配調整、方法検討、事例選定)します。
研究開発方法
気象介入手段として想定している“洋上ドーム形成”、“冷気塊形成”、“海面水温冷却”、“マイクロ波加熱”、“シーディング”を、実際の介入に近い形で数値気象予測モデル(SCALEを想定)に組み込み、特定の豪雨事例を対象にその有効性を定量的に評価します。ここで有望と示された介入手段に関しては、仮想観測システムを計算機上に構築し、その振る舞いを数値的に評価することで屋外実験の実施に向けた計画の策定を行います。
なお、災害緩和のために必要となる海上豪雨の規模や、陸域降雨量の低減量は、災害イベントにより異なると考えられるため、研究開始時点では明確な数値目標を設定しません。
研究プロジェクト全体としては、課題5-2の成果も踏まえ、海上豪雨形成の可能性が高い事例を令和5、6年度に絞り込みます。また、選定された事例に対し、課題8-1、8-2により洪水氾濫計算・経済被害推定計算を進め、どの程度の海上豪雨生成量・陸域降水の低減量が必要か調査し、低減すべき降水量の目標値を、選定した事例ごとに早期に設定し、本課題の目標値としても利用します。
研究開発の重要性
気象介入に関しては、豪雨に関わる流れ場を凌駕する(非現実的なほど莫大な)エネルギーを加えることが出来れば、確実に特定の地域の豪雨を軽減できるはずです。しかし“実現性”は、本プロジェクトにおける中心的なキーワードであり、実際に想定される介入手段に近い形を数値モデル内において表現することは、課題推進の重要な要素の1つです。
また有望な介入手段が見つかったとしても、実際の屋外実験を実施するには、非常に大きな人的・物的資源が必要になります。仮想観測システムを計算機上に構築し、それを実施計画に利用することは、資源の有効活用という点で意義は大きいと考えます。
取り組みにあたり予想される問題点とその解決策
人為的な介入の有効性を示すには、特定の豪雨事例に着目したとしても確率的な議論ができる程度の実験数が必要です。一方で、雲・降水は強い非線形的な過程を含むことから、“確率的な議論ができる程度の実験数”というのは明らかではありません。また数値実験の設定によって内部の系が持ち得る自由度は変わってくるために、実験設定(計算領域の大きさ、解像度、物理過程のパラメタリゼーション)に結果が依存することも考えられます。
当面は推進速度を重視して(出来るだけ)“網羅的” に実験を行いますが、同時に数理研究グループと連携しながら、低次元化したモデルを用いた効率的な数値実験の設定・構成に関する探索手法の確立を目指します。
また本課題では、最初は特定の豪雨事例だけに着目する計画ですが、有効な介入手法はいつも同じではなく事例によって変わる可能性があります。これに関しては、豪雨事例を適当なパラメータを用いてインデックス化するという、研究開発課題5-2と密に連携しながら介入手法の整理を行います。
メンバー

研究開発課題5-2海上豪雨形成の可能性がある事例選定
研究開発課題推進者: 濱田 篤
研究概要
気象庁などの解析データを活用し、介入操作が有効に働いて海上豪雨を形成できる可能性の高い事例を選定します。具体的には、対流抑制エネルギーや、自由対流高度などの空間分布・時間変化を調査して事例を選定します。
豪雨のトリガーとなるメカニズムを気象学的に解明すると共に、有効に働くと期待できる想定する気象介入操作について検討します。
研究開発方法
気象庁が提供するメソ解析および欧州中期予報センター(ECMWF)が提供するERA5再解析データを中心に用いて、過去に顕著な災害をもたらした豪雨事例の中から、気象介入操作が有効に働くと期待される事例を選定します。
気象介入操作として現時点で想定しているのは、洋上ドーム形成、冷気塊形成、海面水温冷却、マイクロ波加熱、およびシーディングですが、これらの多くは大気境界層の暖湿な空気を強制的に上昇させる効果を持ちます。従って、介入操作の有効度は、境界層を中心とした大気の安定度や水蒸気フラックスと相関すると考えられます。介入操作が有効に働くと期待される事例の選定にあたり、陸上豪雨が発生した地点およびその上流の海上における対流抑制エネルギーや水蒸気フラックスが、雨量に与える影響を定量的に評価したうえで、これら物理量を組み合わせて介入操作の有効性を表すインデックスを開発します。
研究開発の重要性
気象モデルを用いて介入操作の効果を評価するには、実際に過去に起こった豪雨事例を適切に再現することが不可避です。災害をもたらす豪雨は多様であり、本プロジェクトが候補に挙げる介入操作は、それら全てに効果を発揮するとは限りません。少数の事例を詳細に解析した結果を、物理量に基づく客観的かつ定量的なインデックスに集約することで、多数かつ多様な過去の豪雨事例から介入操作が有効に働く事例を効率的に選定できると期待されます。
取り組みにあたり予想される問題点とその解決策
介入操作が効果を発揮する豪雨事例の選定およびその効果を表すインデックスの作成のために、多数の事例を詳細に解析して知見を蓄積する必要がありますが、この作業に想定以上に時間がかかる恐れがあります。そのため、まずは1~2事例程度をある程度の妥当性を持って選定し、特に研究開発課題5-1と密に連携しながら、介入効果と相関の高いインデックスの作成を目指します。
メンバー
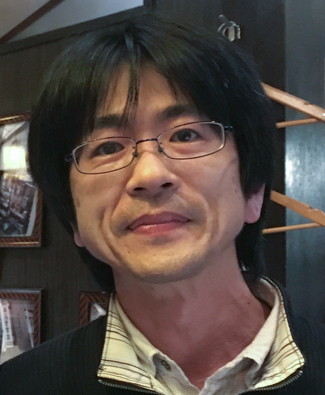
研究開発課題5-3アンサンブル気象予測実験
研究開発課題推進者: 平賀 優介
研究概要
数値気象予測モデル (WRF)を用いて、気象介入手段 (洋上ドーム形成、冷気塊形成、海面水温冷却、マイクロ波加熱、シーディングなど) の有効性を明らかにします。
境界条件・初期値を変えたアンサンブル介入感度実験を実施し、その中から有効な介入を探す帰納的なアプローチで、海上豪雨生成による陸域豪雨の抑制を実現する介入操作を発見します。
研究開発方法
国際的に広く用いられる非静力学気象モデルWeather Research and Forecasting model (WRF)を用いて気象介入の数値実験を実施します。
想定する気象介入パターン(洋上ドーム形成、冷気塊形成、海面水温冷却、マイクロ波加熱、シーディングなど)を実際の介入に近い形でWRFに組み込み、特定の豪雨事例を対象にシミュレーションを実施することで、陸域豪雨の抑制の観点からその有効性を定量的に評価します。
なお、災害緩和のために必要となる海上豪雨の規模や、陸域降雨量の低減量は、災害イベントにより異なると考えられるため、研究開始時点では明確な数値目標を設定しません。
研究プロジェクト全体としては、課題5-2の成果も踏まえ、海上豪雨形成の可能性が高い事例を令和5、6年度に絞り込みます。また、選定された事例に対し、課題8-1、8-2により洪水氾濫計算・経済被害推定計算を進め、どの程度の海上豪雨生成量・陸域降水の低減量が必要か調査し、低減すべき降水量の目標値を、選定した事例ごとに早期に設定し、本課題の目標値としても利用します。
研究開発の重要性
本プロジェクトの目標達成のため、先ずは海上豪雨の生成の可能性、またその有効性を十分に検証することが不可欠です。ここで、実空間における気象介入実験の実施には膨大なコストを要するものの、数値モデル上の仮想空間では様々なパターンで気象介入実験が可能です。これにより、海上豪雨生成に最も有効な介入手段、介入実施の場所、タイミングに関して知見を蓄えることができ、将来的に屋外実験を効率的に実施するために欠かせない知見を得ることができます。
取り組みにあたり予想される問題点とその解決策
WRFモデルによる気象介入操作を意図したアンサンブル実験は前例が少なく、先駆的な研究開発となります。
例えば人為的な気象介入を実施した際、数値計算の安定性に影響を与え、計画通り計算が進まない可能性があります。その場合は、本研究開発課題PIがカリフォルニア大学に在籍した当時よりつながりを有しWRFモデル開発者の1人であるShu-Hua Chen教授に直接意見を求め解決にあたります。
メンバー

研究開発課題5-4クラウドシーディングの物理的な理解と有効性評価
研究開発課題推進者: 端野 典平
研究概要
数値気象モデルを用いて、陸域における降水量の減少や非局所化のためのクラウドシーディング技術の有効性を明らかにします。特に夏季の孤立積乱雲を対象とした数値実験を行い、シーディングによる降水過程の変化を理解すること、またスコールラインにおける降水過程のシーディングへの感度を定量的に推定することを目的とします。
研究開発方法
ドライアイスのシーディングスキームを詳細な雲微物理スキーム(Advanced Microphysics Prediction System; AMPS)に導入し、数値気象予測モデル(The University of Wisconsin nonhydrostatic modeling system; UWNMS)を実行します。シーディングの有効な時間と場所を感度実験によって特定します。
またモデル開発にあたっては、プロジェクトが2025年度から実施計画している航空機によるシーディング・フィールド実験や、筆保プロジェクトにおいて2026年度に導入が計画されている雲チャンバー実験と協働し、モデルの精緻化を行います。
研究開発の重要性
これまでの項目5によるプロジェクト活動から、クラウドシーディングが気象制御に対して有効な介入手段であることが示されてきました。しかしながら、シーディングには過冷却水の分布(時間と場所)について、定量的な理解が必要です。また、孤立積乱雲や線状降水帯に対して、シーディングを行なった時の振る舞いの理解を深める必要があります。その手段として力学と雲の情報を再現する数値モデルの利用が有効です。
過冷却水滴の分布は上昇流の強さのみならず、エアロゾル粒子の特性と量に依存するため、これらを数値的に再現することが重要です。一般に、気象予報に用いられる雲降水の数値モデルは、エアロゾル粒子の動態は考慮せず、計算負荷を減らすため雲降水粒子に粒径分布や粒子種の仮定を導入しています。シーディング後の雲と降水の物理過程の変化を理解するには、これらの仮定を取り除き、エアロゾル粒子を予測する詳細な物理モデルを用いる必要があります。
取り組みにあたり予想される問題点とその解決策
過冷却水滴の分布は、与える熱源の強さや背景となるエアロゾル粒子に依存します。しかしながらエアロゾル粒子の濃度や特性について、地上付近以外では観測されていません。これらを典型的な値から変化させながらどの程度、過冷却水滴が変化するか、把握する必要があります。本研究で用いるAMPSは、極域や高緯度の雲降水現象について再現し、検証してきました。積乱雲の再現についてはまだ事例が少ないので、レーダー観測など用いながら検証とモデルの改良を進めてゆきます。
メンバー

研究開発課題5-5介入効果の地上観測検証
研究開発課題推進者: 吉見 和紘
研究概要
気象介入操作の効果を地上観測により定量的に検証するための観測体制を構築することを目的とします。プログラム5年目までは、海上シーディング実験を想定し、気象レーダーと地上観測装置を組み合わせた可視化・観測体制の高度化を図ります。また、構築した観測網に加え、可搬型気象レーダーの設置による効果検証の検討、ドローンと降水粒子撮像ゾンデの組み合わせなど、機動的観測による介入操作の検証手法の研究開発を進めます。
研究開発方法
本研究では、気象介入操作の効果を定量的に可視化・検証するための観測手法を開発します。
2025年度は、冬季に計画されているシーディング実験を念頭に、国交省が運用するXバンド二重偏波レーダー等を活用し、仰角・高度・方位角・時間分解能等のパラメータを最適化し、シーディング効果の検証を支援するためのレーダー・データ可視化アルゴリズムを開発します。同時に、地上雨量計やディスドロメータなどの降水粒子観測機器を用いた設置型観測の構成と運用手順を検討し、実験時の観測体制を確立します。
2026年度は、可搬型気象レーダーの運用による観測網の拡張について検討するとともに、全天候型ドローンと降水粒子撮像ゾンデを組み合わせた機動観測を導入し、シーディング効果の鉛直構造や局地的分布を詳細に捉える手法を開発します。これにより、静的な観測と動的な観測の両面から介入効果の評価を行い、高精度かつ現場適応可能な観測フレームの確立を目指します。
研究開発の重要性
気象制御技術においては、介入操作の効果を科学的に評価するための高信頼な観測手法の確立が不可欠です。しかし現状では、シーディング等の操作が降水に与えた影響を直接的に捉える観測技術は限られており、その有効性を社会的に説明可能なエビデンスに基づいて示すことが困難です。
本研究では、全天候型ドローンによる降水粒子観測や、気象レーダー等を用いた三次元降水構造の解析手法の知見を活かしつつ、静的・動的な観測手法を融合させることで、従来にない高密度かつ空間的に柔軟な検証体制の構築を目指します。特に、気象制御に関して、実験場を海上とするフィールド研究は国内でも希少な取り組みであり、本手法の確立は将来的に、高高度帯の雨雲への観測・介入や、局地的豪雨の制御といった先進的な気象制御の実装に向けた観測技術の中核を担うものです。本研究は、気象制御の科学的妥当性と社会的受容性の両立に向けた基盤整備に大きく貢献します。
取り組みにあたり予想される問題点とその解決策
本研究においては、複数の観測機器(気象レーダー・地上センサ・ドローン等)の同期運用や、その空間・時間的整合性の確保が技術的な課題となる可能性があります。これに対しては、各観測機器の仕様に応じた観測タイミングの調整や、後処理による解析手法の工夫により対応します。また、海上でのフィールド観測に伴う気象・海象条件の変動や、運用面での安全確保も考慮すべき課題です。これらに対しては、過去の観測経験をもとに、十分な予備期間の確保および段階的な運用試行を実施することで、柔軟かつ確実な運用体制の構築を目指します。
メンバー